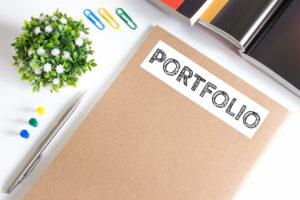在宅介護における身体拘束
身体拘束とは一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限の事を指します。
例えば、次のようなケースがあります。
- 認知症の徘徊症状で勝手に外出するため、本人が部屋の中から開けられないような鍵を付けた
- おむつを外してしまうので、ツナギの洋服を着せている
- 転倒の危険があるので、車いすから立ち上がらないように、車いすと身体をベルトで固定した
これらの行為は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設では身体拘束にあたり、禁止されていますが在宅で介護をしている場合にはどうでしょう?
家から勝手に出て行ってしまえば一人で帰って来れなくなるかもしれませんし、交通事故に合う危険性もあります。
そして、頻繁に徘徊する方を介護している家族にとっては、そのたびに本人を探さなければならず、時間も労力もかかるうえ、何より本人の安否が心配です。
オムツを外され尿失禁や便失禁をした場合、家族はそのたびに洋服を着替させ、汚れてしまった衣類やシーツ類の洗濯もしなくてはなりません。
ちょっと目を離した隙に、車いすから立ち上がり転倒し、骨折してしまったら入院になる可能性があり、もしかするともう家には戻ってこられなくなるかもしれません。
家族からすれば、困った行為を未然に防ぐ手段のひとつですが、好んで身体拘束をする家族はいないと思います。
可哀そうだけど仕方ない…、そんな思いを抱いている家族も多いはずです。
しかし身体拘束は、本人にとって自分がしたい行動を抑制されていると感じ、自分が思うように行動ができないことに対して、怒りや不安・ストレスを感じているかもしれません。
その怒りや不安・ストレスは、やがて本人の自発性を失わせ、ADLの低下を引き起こし、介護拒否にも繋がる可能性があるのです。
今回は、そもそも何が身体拘束にあたるのか、やむを得ない場合はどんな対応をすればいいのか等を解説します。
身体拘束になる行為
では、どんなことが身体拘束にあたるのでしょうか?
厚生労働省が示している介護施設に対しての「身体拘束ゼロへの手引き」には、禁止の対象となる具体的な行為として以下のような11の項目を挙げています。
- 徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに退官や四肢をひも等で縛る
- 転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を搔きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける
- 車いすかやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト車いすテーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人の迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
「身体拘束ゼロへの手引き~高齢者ケアに関わるすべての人に~」厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より
病院では身体拘束は認められている
介護施設では身体拘束は禁止されていますが、病院では医師の指示があれば身体拘束は認められています。
現に、私の父や母が入院した際には「身体拘束の同意書」にサインをしました。したと言うより、同意をしないと入院させてくれないと言ったほうが適切かもしれません。
私の母は認知症で、初めての場所や初対面の人に対しては強い拒否を示します。
母が救急搬送され、病院に駆けつけたときにはすでに身体拘束をされていました。
身体の何ヶ所かをベルトで固定されていて、まるでガリバー旅行記か!と思ったほどです。
ベッドに縛られていることを理解できない母は「なにをする~、これとってよ~」と大声で叫んでいました。
母はどんなに怖かった事でしょう。
思わず看護師に「ここまで拘束しなくても…」と言ったら、「転倒のリスクがありますから」と言われました。私は内心「母は一人で立てませんから」と言いたかったぐらいです。
身体拘束が可能な病院でも、徘徊しないようにひもで縛る行為はないと思っていましたが、先日のニュースで、ある病院が患者さんをひもで縛っている映像を見たときには、拘束帯でなくひもなの?と流石に驚きました。
これも身体拘束にあたる
在宅では四六時中、要介護者のそばにいることは不可能です。徘徊や転倒の危険があれば、ある程度の身体拘束はやむを得ないことでしょう。
私の父は認知症で(両親共に認知症です)在宅で私と一緒に暮らしています。数年前、深夜2時頃になると勝手にお出掛けしていたことがありました。俗に言う徘徊です。
その頃の私は、玄関のドアがバタンと閉まる音で目が覚めて、慌てて玄関に行くということを繰り返しでした。
いつも玄関を出たところで父を発見していたので、夜な夜な街中を捜索することはありませんでしたが、私が玄関の閉まる音に気が付かなければ、父は深夜の暗闇を歩き回っていたことでしょう。
徘徊を未然に防ぐために、施設ではベッドの下にセンサーマットを設置していケースがあります。利用者がセンサーマットの上を歩くとチャイムが鳴る仕組みです。
ちなみに、センサーマットは利用者の行動を抑制しないので、身体拘束にはあたりません。
センサーマットを設置しようかとも考えましたが、父がトイレに行くたびに大音量のチャイムが鳴り響いたら、私は寝ていることもできません。
そこで私は、玄関の鍵を開けても扉が開かない方法を考え、玄関の蝶番を結束バンドで縛りました。この作戦は見事に成功し、鍵を開けても扉が開かないため父は外へ出られません。
しかしこの方法は、施設の場合だと11番の「自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する」にあたります。
身体拘束が認められる3つの条件
「じゃあ、どうすればいいのよ」という声が聞こえてきますが、身体拘束が認められる3つの条件があります。
厚生労働省が施設に対して示している条件です
切迫性
利用者本人または、他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
身体拘束に該当するとしても、この3つの条件を満たし専門性に基づいた組織的検討を行った上で、客観的に必要とされた場合にのみ、緊急でやむを得ない場合として、例外的に認められています。
その上で本人や家族に説明し、その都度記録をして定期的に見直すこととされています。
ですから多くの施設では、やむを得ず身体拘束をする場合には家族に説明をし、同意書にサインをもらっています。
そして、このような手続きのないまま行われる身体拘束は虐待とみなされるのです。
私が父の真夜中のお出掛けを阻止するために行った、蝶番を結束バンドで止める作戦は、身体拘束が認められる3つの条件にうち、②の非代替性(身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと)にあたるでしょう。
身体拘束の弊害
安易に拘束することは、身体的弊害として拘縮や筋力低下、食欲や心肺機能の低下に繋がることもあります。
また、精神的弊害として、不安・怒り・屈辱・あきらめなどの精神的苦痛で、かえって認知症の症状が進行することがありますし、諦めは本人の意慾を奪い、自らの意思で行動することが減るためADLの低下に繋がります。
ADLが低下すれば、今まで一人でできていたことが減るため、家族にかかる介護の負担が増すことになり、今以上に介護が大変になることは明白です。
身体介護を回避する工夫
では、身体拘束をせずに本人の意思を尊重しながらも、家族からすれば困った行為を未然に防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?
前述した事例をもとに考えてみます。
声を掛ける
私の父もそうですが、徘徊するのは本人なりの理由があるのです。
子どもを幼稚園に迎えに行く、食事の用意をするために買い物に行くなど、元気だった頃にルーティンとして行っていた行動をしようとするケースが多いようです。
ひとそれぞれ理由は異なりますが、出掛けなければならない理由があるからとされています。
例えば、幼稚園のお迎えや買い物に行くケースの場合は「今日は代わりに私が行くね」と、声を掛けてみてはいかがでしょうか?案外「あらそう!じゃあ今日は家にいるわ」と、なるかもしれません。
身体拘束で行動を抑制しないために、まず、徘徊の理由を探して解決策を考えてはどうでしょう。
ちなみに、父の真夜中の徘徊の理由は「皇居で行われる皇室会議に参加するから」でした。
早めのおむつ交換
おむつを外す理由を考えます。
例えば、排せつ物が溜まっていて気持ちが悪いや、皮膚の状態がわるくて痒い等が考えらるので、排せつのリズムを摑んで早めにおむつの交換をする。
皮膚状態を確認して処置(薬を塗布する)などの対策をしてみることも有効だと思います。
行動理由を考えてみる
立ち上がろうとする理由を考えます。
例えば、長い間車いすに座っていたのでお尻が痛い、車いすが身体に合わず座り心地が悪い、今いる場所から移動したい等が考えられます。
立ち上がろうとすると、危ないから座っていて!と言ってしまいがちですが、立ち上がろうとするには理由があるはずなので、どうしたの?と一声かけ、立ち上がりたい理由を聞いて対処すると良いでしょう。
家族が思う「要介護者の困った行動」は人それぞれです。
身体状況や環境により解決策もそれぞれ異なるため、正解がないところが介護の難しさです。
在宅介護では、介護される人の行動を抑制をせず、介護する人がずっとそばで見守りをすることは、ほぼ不可能ですし、介護される人のことを考えすぎて介護する人がず~っと我慢をしていては、介護者が疲れ果ててしまいます。
在宅介護における身体拘束はとても難しい問題ですが、要介護者の困った行動を頭ごなしに抑制するのではなく、要介護者の困った行動の理由を探り、解決することで要介護者も家族も少しは楽になるかもしれません。