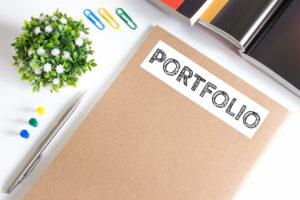特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームに比べ、自由に生活ができることが魅力とされている、サービス付き高齢者向け住宅が近年、爆発的に施設の数が増えています。
しかし本来、自由度の高いはずのサービス付き高齢者向け住宅がなのですが、そうではないいサービス付き高齢者向け住宅が増えているようです。
サービス付き高齢者向け住宅は高齢者が安心して生活できる賃貸住宅
厚生労働省のHPには、サービス付き高齢者向け住宅について、次の表に表記されています。
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度です
登録の基準は、次の通りです。
- 各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
但し、居間・食堂・台所・その他の住宅の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は、18㎡以上 - 各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
但し、共用部分に共同して利用するため適切な台所・収納設備・浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所・収納設備・浴室を備えずとも可 - バリアフリー構造であること
安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中、建物に常駐し、これらのサービスを提供します。
簡単に説明すると、バリアフリー構造で居室の面積は原則25㎡以上。居室内に水洗便所があり、ケアの専門家による安否確認と生活相談サービスが付いている住宅ということになります。
つまり、サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認と相談できるサービスが付いたバリアフリー構造の賃貸住宅と言い換えることができます。
また、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームは厚生労働省が管轄していますが、サービス付き高齢者向け住宅の都道府県知事への登録制度は国土交通省と厚生労働省の共管制度となっています。
創設当初の入居条件は自立か要支援
平成23年の創設当初、高齢者向けビジネスの新たな展開を見込んだ多くのハウスメーカーなどが、サービス付き高齢者向け住宅事業に乗り出しました。
当時は買い物などが便利な立地にあり、高級感のある外観の作りが多かったように記憶しています。
しかし、多くのサービス付き高齢者向け住宅は入居者が入らず、何年経っても満室にならない施設もありました。
満室にならない理由のひとつとして、考えられるのが入居時の条件です。
創設当初は、多くのサービス付き高齢者向け住宅は、入居条件を自立か要支援としていました。
入居後に介護が必要になった場合は、重度にならない限り住み続けられていましたが、あくまでも入居時はある程度自分のことは自分でできる方を対象としていました。
しかし、自立や要支援の人が一人暮らしに不安を抱えていたところで、住み慣れた自宅を離れ、近所のコミュニティを手放してまで、新しい場所に引っ越すでしょうか?
高齢になればなるほど、新しい環境になじむのには時間がかかります。そんな理由もあり、鳴り物入りでスタートしたサービス付き高齢者向け住宅でしたが、どこの事業所も入居者集めに苦戦していました。
入居条件を要介護も対象に変更
施設は建てたが、入居者が入らないでは運営が成り立ちません。そこで多くのサービス付き高齢者向け住宅は、施設内で介護保険以外のサービスを、24時間提供する職員を配置するなどし、入居時の条件を「要介護も可」としました。
サービス付き高齢者向け住宅に入居して介護を受けるには、外部の居宅支援事業所と契約し、どこのデイサービスを利用するか?
どこの訪問介護事業所を利用するかをケアマネジャーと相談し、それぞれの事業所と契約をしてケアプランを作成してもらい、介護のサービスを利用しながら生活をします。
入居時の条件を、要介護も可としたこともあり、サービス付き高齢者向け住宅イコール介護が必要な人が入居する施設というイメージとなりました。
また、介護付有料老人ホームに比べて比較的安い価格で入居ができることや、自由に外出できる(※)ことなどもあり、サービス付き高齢者向け住宅に入居する人が増えてきました。
ここで重要なキーワードは「外部」です。創設当初のサービス付き高齢者向け住宅には、居宅支援事業所や訪問介護事業所、デイサービスなどは併設されていませんでした。
介護が必要な方は、近隣の事業所と契約をして、介護保険サービスを利用しながら生活されていたのです。
※残念ながら、現在ではコロナウイルスが蔓延していることもあり、以前のように自由には外出できないようです。
訪問介護の併設
多くのサービス付き高齢者向け住宅は、オーナー(土地の所有者)に建物を建ててもらい、数十年(20年~25年)の間賃料をオーナーに支払うと言う方法で運営しています。
これは、施設が満室であっても入居者が0人であっても、毎月オーナーには賃料を支払うという仕組みです。
しかし、この仕組みは一定の入居者がいなければ、赤字運営になってしまうということです。
少しでも運営をプラスにするため、入居者が外部と契約していた介護保険サービスを自社と契約してもらい、介護保険サービスから収益を得ようと考えた事業所が現れ始めました。
訪問介護の事業所が施設内に併設されているところもあり、介護保険のサービスは施設内のヘルパーさんが提供しているところもあります。
デイサービスの併設
デイサービスが併設されている、サービス付き高齢者向け住宅が増えてきています。
施設内にデイサービスが併設されていれば、雨が降っても、雪が降っても濡れることなくデイサービスに通えますが、問題点も指摘されています。
入居条件は、併設しているデイサービスを利用するという縛りを設けているサービス付き高齢者向け住宅の存在です。
100歩譲って、この条件でも入居者がOKとするならば良いでしょう。
しかし最近、私が相談を受けたAさんからの事例には驚きました。
Aさんは、要介護3で認知症はありません。賃貸マンションに一人で暮らしていましたがこの先のことを考え、サービス付き高齢者向け住宅に入居されました。
併設のデイサービスを利用することが入居の条件だと知っていましたが、新築にも関わらず家賃も食費も安いので入居を決めたそうです。
本当は、お友達のいる今までのデイサービスに通いと思ったそうですが、自由にデイサービスを選べるところは、利用料が高額で支払いが難しいと判断されたそうです。
Aさんはこれまで通り、週に3回ほどデイサービスを利用しながら、ゆっくりとした生活ができると思っていましたが、現実は思っていた暮らしと違っていたのです。
毎朝、職員がデイサービスに行きましょうと声をかけてくる。
今日は部屋でゆっくりしたいと話をしても、デイサービスに行かないと昼食が食べられないとか、1日中、部屋にいるとつまらないでしょう?などと声をかけられ、行かなくてはいけない雰囲気になってしまうことが苦痛だとおっしゃいます。
この状況からAさんのケアプランには、毎日のデイサービス利用が組み込まれているのではないかと想像がつきます。
本来ケアプランは、本人の意向や希望が組み込まれなくてはならないはずですし、介護保険サービスは利用者が自由にサービスを選べる仕組みでもあるはずです。
しかし残念ながら、Aさんが入居されたサービス付き高齢者向け住宅では、本人の希望よりも特定法人(サービス付き高齢者向け住宅と同じ)のサービスを優先したプランになっているようです。
なぜこんなことが起きるのでしょうか?
それは入居者の意向や状態を考慮せず、サービス付き高齢者向け住宅事業者と同一法人によるサービスをケアプランに設定しているからで、介護保険の収入を多くしたい意向なのだと考えられます。
入居前に細かく確認
サービス付き高齢者向け住宅に、デイサービスや居宅支援事業所・訪問介護事業所が併設されていることが問題なのではなく、入居者がサービス事業者やサービス内容を、自身で選択できないことが問題なのです。
安い家賃や食費で入居者を集め、併設しているデイサービスや訪問介護を利用することが条件になっているサービス付き高齢者向け住宅もあります。
家賃や食費が安くても、区分支給限度額上限までのサービスが設定されている場合には、介護保険の自己負担額が高くなり、1ヶ月の利用料の負担は大きくなります。
厚生労働省は、ケアマネジャーに対して、次の事例を過剰なサービスとして注意喚起を行っています。
入居者の意向や状態を考慮せず、アセスメントからは必要性が見いだせない住まい事業者と同一法人によるサービスをケアプランに設定している。その結果として区分支給限度額上限までサービスが設定されている。
サービス付き高齢者向け住宅を選ぶ際には、一ヶ月の家賃や食費の安さばかりに気をとられずに、入居後の介護保険サービスを、どこから受けることができるのか?自身の意向や家族の意向をケアプランに反映させてもらえるのか?ある程度の自由な暮らしが提供されるのか?などを、考慮してみることが大切です。